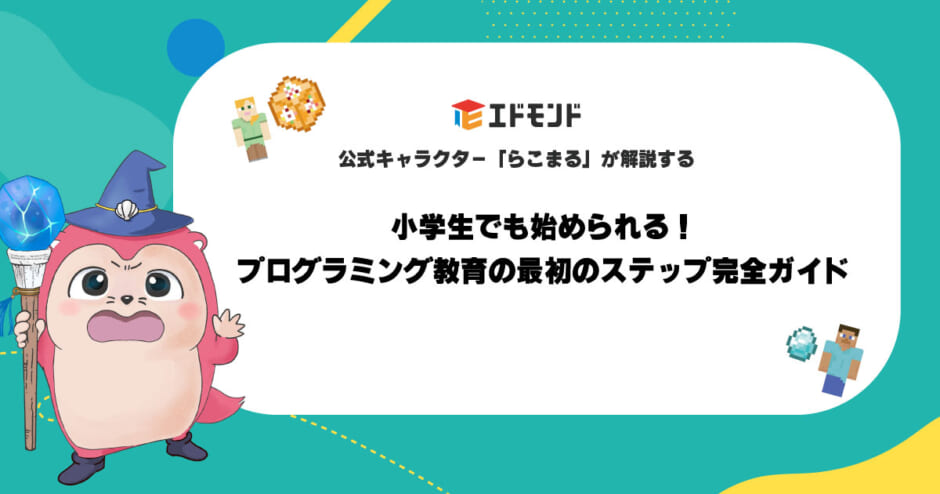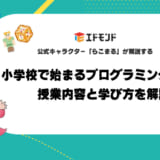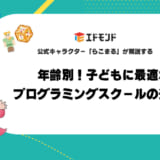- はじめに
- プログラミング教育の基礎知識
- プログラミング教育のメリット
- 小学生向けプログラミング教育の種類
- プログラミングスクールの選び方
- プログラミング学習を成功させるための家庭でのサポート
- 実際にプログラミング教育を始めた保護者の声
- まとめと次のステップ
1.はじめに
ねぇ、ふと周りを見てみると、スマホやパソコンだけじゃなくて、冷蔵庫や車とか、身の回りのものってほとんどコンピュータが入ってるって知ってた? たとえば、自販機だって、お金を入れてボタンを押すだけなのに、ちゃんと在庫管理や温度調整とかまでプログラムで動いてるんだよ!なんかすごいよね。
こんなふうに、コンピュータとプログラミングってもう私たちの生活にしっかり入り込んでるんだよね。しかも、AI(人工知能)がもっと進化していくこれからの時代、小学生がコンピュータを使いこなしていく力って、絶対に必要になってくるんだ。
でもね、プログラミング教育って、ただ「コードが書けるようになること」だけが目的じゃないんだよ。むしろ大事なのは、「どうやって物事を考えて、順序立てて解決していくか」っていう論理的な思考力を育てることなんだって。で、この力って、すぐに身につくわけじゃなくて、小学生の頃からコツコツと積み上げていくのがポイントらしいよ。
文部科学省の調査でも、プログラミング教育で培われる論理的思考力って、算数とか理科だけじゃなくて、国語や社会の勉強にも役立つことが分かってるんだって!特に小学生のうちに、この基礎をしっかり作ることが大事なんだよね。一人ひとりのペースに合わせた学びが、めちゃくちゃ大切なんだって思う。
たとえばね、ビジュアルプログラミングツールを使って、自分だけのゲームやアニメーションを作ったり、正多角形を描くプログラムで図形について学んだりするんだって。センサーを使った制御プログラムなんかもやるみたい!こういう体験を通じて、「楽しい!」って感じながら力をつけていけるのがいいよね。
それに、保護者の方も「いつから始めたらいいの?」「家庭で何をしてあげたらいいの?」って悩むことあるよね。プログラミング教育って、小学生の発達に合わせて進んでいくから安心して大丈夫!低学年のうちはゲーム感覚で楽しく学んで、中学年・高学年になったら少しずつ本格的な内容に進んでいく感じ。それぞれの興味やペースを大事にするのが、一番いいんだよね。
家庭でできるサポートとしては、子どもが「これ面白そう!」って思ったときに一緒にプログラミング体験してみたり、日常の中で「これってどうやったらうまくいくかな?」って声をかけたりするのが効果的だよ。料理のレシピを考えるとか、片付けの順番を考えるみたいな日常の場面でも、プログラミング的な考え方が自然と身につくんだって!
今、世界中でプログラミング教育がどんどん広がってて、日本でも2020年から小学校で本格的にスタートしてるよね。小学生のうちからこういう力を育てていくと、未来社会での問題解決能力がすごく伸びるんだって。実践的な学びを通じて、しっかりした力が育まれるって、なんか心強いよね。
じゃあ具体的に、プログラミング教育が小学生にどんな良い影響を与えるのか、そして家庭でどうサポートすればいいのか、これから詳しく見ていこうね!
[参考文献]文部科学省「小学校段階におけるプログラミング教育の在り方について」
文部科学省「小学校プログラミング教育の手引(第三版)」
https://www.mext.go.jp/content/20200218-mxt_jogai02-100003171_002.pdf
2.プログラミング教育の基礎知識
プログラミング教育って聞くと、「なんだか難しそう」「パソコンの操作が複雑なんじゃない?」って思う人も多いかもしれないよね。でも実際には、プログラミング教育ってコンピュータの使い方を教えることが目的じゃないんだよ。
本当に大事なのは、「どうやったら自分が考えた通りに動かせるか」を順序立てて考える力、つまり論理的な思考力を育てることなの。これをプログラミング的思考って呼ぶんだけど、小学生の成長に合わせて、少しずつこの力を伸ばしていくのがプログラミング教育のポイントなんだ。
たとえば、朝の準備を例に考えてみて!起きてから学校に行くまでに「どの順番で何をするか」って考えることって、プログラミング的思考そのものなんだよね。効率よく進めるために手順を工夫することも、実はプログラミングの考え方とすごく似てるの。こんな風に、プログラミング教育って生活の中で自然と身についていく力と密接に関係してるんだ。
文部科学省の調査では、この論理的思考力が算数や理科だけじゃなくて、国語や社会といった教科の学びにもいい影響を与えるってわかってるんだって。特に小学生のうちは、論理的な考え方の基礎を作る大事な時期だから、今のうちから育てておくことがすごく重要なんだ。
じゃあ、具体的にどんなふうに効果が出るのか見てみようよ。たとえば算数なら、図形の特徴を考えたり、規則性を発見したりする力が伸びるんだって。理科では、実験結果を整理して原因を考える力が高まるし、国語では物語や説明文の構成を論理的に組み立てる力が鍛えられるんだよ。さらに、総合的な学習の時間では、課題を解決するための情報整理やアイデアの発案にプログラミング的思考が活かされるんだって!
たとえば、川崎市では子どもたちの年齢や理解度に合わせて、プログラミング教育を段階的に進めているんだよ。低学年では、身近な生活の中で具体的な例を使って、中学年では簡単なプログラミング体験、高学年になると教科と連携した本格的な学習に進んでいくんだって。
実際の授業では、算数で正多角形をプログラミングで描いたり、理科でセンサーを使って電気の学びを深めたりする活動が行われてるんだ。総合的な学習の時間では、身近な問題を解決するためのアイデアをプログラムにしてみることもあるんだよ。こうした学びの中で、子どもたちは「どうしてそうなるの?」とか「もっとよくするにはどうすればいい?」って自分で考えて、いろんな試行錯誤を繰り返していくの。
何より大事なのは、一人一人のペースや興味に合わせて、無理なく力を伸ばしていくことだよね。プログラミング教育って、テストで「できる・できない」を決めるものじゃなくて、「自分で考えてやってみる力」とか「諦めずに挑戦する姿勢」を育てることに重きを置いてるの。
こういう学びを通じて、子どもたちはただパソコンを使えるようになるだけじゃなくて、物事を論理的に考えたり、自分のアイデアを形にして問題を解決する力をどんどん身につけていくんだ。それって、どんな仕事に就くとしても絶対に役に立つスキルだよね。さらに、自分から積極的にデジタル技術を活用できる力も自然と身についていくんだから、ほんとに素敵なことだと思うの。
プログラミング教育って、何か特別なことをするんじゃなくて、未来を切り拓く力を育てるためのすごく大切な学びなんだよね。だから、親としてもその意義をしっかり理解して、子どもの挑戦を温かく見守ることが大事だと思うんだ。
[参考文献]文部科学省「小学校段階におけるプログラミング教育の在り方について」
川崎教育研究所「小・中学校におけるプログラミング教育の研究」
https://kawasaki-edu.jp/index.cfm/7,146,c,html/146/32-093-112.pdf
3.プログラミング教育のメリット
ねえ、みんな知ってる?小学生のプログラミング教育って、ただ論理的思考力を伸ばすだけじゃないんだよ。会津大学の研究によると、プログラミングを通じて、小学生の思考力とか判断力、問題解決力とか、いろんな認知能力がググッと成長するんだって!特に、小学生の時期って、そういう体系的な思考力を育てるのにめっちゃ大事なタイミングなんだよね。
でね、プログラミングがどんな風に役立つかっていうと、まずは論理的思考と創造力の部分!小学生がプログラミングをやると、ゴールを達成するために必要な動きを順番に考えて、それをどう実行するかを組み立てるの。これが結構面白くて、「こうやったらうまくいくかな?」っていろいろ試して、失敗して、また考え直す。その繰り返しで「どうやったら問題が解決できるか」を考える力がどんどんついていくんだ。たとえば、プログラムが思い通りに動かなかったら、「あれ、どこが間違ってる?」って原因を探して直してみる。この一連の流れが、すごくいい経験になるんだよね。
そしてね、プログラミング教育って、ただ学校の成績を上げるだけじゃなくて、将来の可能性も広げてくれるの。今の社会って、どんなところでも情報技術が使われてるじゃん?だから、小学生のうちにプログラミングの基礎を学んでおくと、いろんな職業とか活動にチャレンジしやすくなるんだって!論理的に考えて、効率よく解決する力って、どんな仕事でも役立つ基本スキルだよね。それを小学生の頃から育てられるなんて、すごくない?
あと、教科へのいい影響も見逃せない!算数だと図形の性質とか規則性がもっとわかるようになるし、理科だと実験の計画とか結果の分析が上手になるんだって。国語でもね、文章をどう組み立てたらいいか考えられるようになるみたい。つまり、プログラミングで培った考え方が、いろんな教科にいい影響を与えてくれるってこと!
それだけじゃないよ。プログラミングをやると、子どもたちの学習意欲がすごくアップするの。だって、自分で考えたことが目の前で動いたらめちゃくちゃ嬉しいじゃん?「やった!できた!」っていう達成感が次のやる気につながるんだって。こういうポジティブな気持ちが、学校の勉強にもいい影響を与えるんだよ。
しかも、プログラミングをやると情報を扱う力もついてくるの。例えば、必要な情報を集めたり、それを整理して分析したり、最終的にどう使うかまで考えられるようになるの。これって、将来デジタル社会を生きるためにはめちゃくちゃ大事なスキルだよね。
で、もう一つのポイントがコミュニケーション能力!プログラミングの授業って、ただ一人で黙々とやるだけじゃなくて、グループで課題に取り組むことも多いの。その中で自分の意見を伝えたり、他の人の考えを聞いたりする経験が、コミュニケーション力をぐんと伸ばしてくれるんだよ。特に、みんなで協力して問題を解決するっていう経験が、将来社会で活躍する力につながるの、すごいよね。
あとね、プログラミングで学ぶ「目標を立てて、それを達成するためのプロセスを考える力」って、実は日常生活にも役立つんだ。たとえば、宿題をどうやって効率よく終わらせるかとか、どの順番でやるのがいいか考えられるようになるんだよ。時間の使い方が上手になるなんて、めちゃ便利じゃない?
さらに、創造性もバッチリ育つの!課題に対して「どうすればもっといい方法がある?」とか「このやり方、面白くできないかな?」って考える機会が多いから、新しいアイデアをどんどん生み出す力がついていくんだ。しかも、同じ課題でもいろんな解決策があるってわかると、柔軟な考え方も身についてくるんだよ。
こんなふうに、小学生のプログラミング教育って、論理的思考だけじゃなくて、創造力や問題解決能力、コミュニケーション力まで、いろんな力を育ててくれる素晴らしい活動なんだよね。しかも、学校での学びにとどまらず、家庭や将来の社会生活にも活かせるから、早いうちから始めるのが本当におすすめ!
[参考文献]会津大学「プログラミング教育における作問学習による学習効果向上の定量的評価」
https://www.jc.u-aizu.ac.jp/news/management/gr/2019/04.pdf
4.小学生向けプログラミング教育の種類
小学生の学びって、その年齢に合った工夫が本当に大事だよね。小学校でのプログラミング教育も、子どもたちの発達に合わせて、いろんな方法で進められてるんだよ。
今、小学校では主に3つの形でプログラミング教育が行われてるんだ。一つ目は教科の授業での実践!たとえば、算数の時間に正多角形を描くプログラムを作ったり、5年生の理科でセンサーを使って明かりをつける実験をしたりしてるの。こういう活動って、ただの勉強じゃなくて「なんでこうなるの?」って考える力を自然に育ててくれるんだよね。
二つ目は、総合的な学習の時間での取り組み。ここでは身近な地域の課題を見つけて、その解決策を考えたりするの。たとえば、地域の観光案内をデジタル化したり、防災情報をもっと分かりやすく伝える仕組みを考えたりするのって、なんかカッコいいよね!
三つ目は、クラブ活動とか課外活動。もっと深く学びたい子のために、発展的な学びが用意されてるんだ。子どもたちは興味に合わせて、自分でどんどん学べるって素敵じゃない?
実際の授業では「ビジュアルプログラミング」っていうやり方が多く使われてるの。これ、命令をブロックみたいに組み合わせていく方法で、小学生でも直感的に操作できちゃうんだよ。マウスとかタッチパネルで操作できるから、キーボードを使う必要もなくて、ほんとに気軽に始められるの。
でもね、いつもパソコンばかり使うわけじゃないんだ。低学年のうちは「順序立てて考える」練習を日常の中でやったり、紙と鉛筆で手順を考える活動も取り入れてるの。こうやって無理なく論理的思考力を育てていくんだよ。
学年ごとに学ぶ内容もちゃんと工夫されてるんだよ。1、2年生では生活科と連携して、日常の中で順序を考える練習。3、4年生では図工でプログラムを使って絵を動かしたり、音楽で音を組み合わせたりして楽しみながら学べるの。5、6年生になると、教科と結びついた本格的なプログラミング体験に進むの。ここまで来ると、かなり本格的で面白いんだよね!
特に教科との連携がすごく大事にされてるんだよ。たとえば、6年生の理科ではエネルギーの効率的な使い方を学ぶ中で、自動点灯の仕組みを考えたりするの。算数では、図形の性質を深く理解するためにプログラムを活用するんだって。
さらに、小学生同士でのグループ活動も大切にされてるの。「ここをこうしたらもっと良くなるんじゃない?」とか「別のやり方を試してみようよ!」って話し合いながら、一緒に解決方法を見つけていくんだよ。この過程で、みんなの考えがどんどん広がっていくのが面白いよね。
家庭でのサポートもすっごく大事!親が子どもの話を聞いてあげたり、「すごいね!こんなこと考えたんだ!」って認めてあげたりすると、子どもたちはもっと頑張ろうって思えるんだよ。学校でやったことに興味を持って、一緒に考えるのもいいよね。それが、子どもの学びをぐっと深めてくれるんだ。
こうして小学校でのプログラミング教育は、子どもたちの成長に合わせて、楽しみながら論理的思考力を育てるように工夫されてるの。これが教科の理解を深めたり、問題解決能力を高めたりするだけじゃなくて、家庭でもその考え方が生かされるんだよ。たとえば、宿題を計画的に進めたり、部屋の片付けをもっと効率よくしたりする場面で、プログラミング的な思考が自然に発揮されるのって素敵だよね!
[参考文献]文部科学省「小学校プログラミング教育の手引(第三版)」
https://www.mext.go.jp/content/20200218-mxt_jogai02-100003171_002.pdf
5.プログラミングスクールの選び方
小学生の習い事として「プログラミング教室」を選ぶなら、どんなポイントに注目すればいいのかな?最近はいろんな教室があって目移りしちゃうけど、子どもの可能性を広げてくれる素敵な場を選ぶのが大事だよね。ここでは、具体的な選び方のポイントをわかりやすくお話ししていくね!
まず一番大事なのは、子どもの成長段階に合ったカリキュラムがあるかどうか。小学生って、学年ごとに理解力や興味の幅が全然違うから、画一的な内容じゃなくて、その子のペースや好奇心に寄り添ってくれる仕組みが整っているかをチェックしてみてね。
次に気になるのが、学校の教科学習とのつながり。算数や理科の授業内容とリンクしてるプログラミング教室だと、学校での学びがさらに深まるっていうメリットもあるよ。だから、指導方針に「学校との関連」を意識した内容があるかどうか、確認してみるといいかも。
あと、体験会に参加するのは本当におすすめ!実際の授業の雰囲気や先生の教え方をその場で感じられるし、何より子ども自身が「ここ、楽しそう!」って思えるかどうかが一番大事。多くの教室で体験会は無料だから、ぜひ気軽に参加してみてね。
それから、先生の質も見逃せないポイントだよ。技術的なスキルが高いだけじゃなくて、子どもの気持ちに寄り添ってやる気を引き出してくれる先生かどうか、体験会のときにしっかり観察してみて。小学生には「楽しい!」と思わせてくれる先生がぴったりだよね。
教室のスタイルも色々選べるよ。通学型は直接先生や友達と顔を合わせて学べるから、コミュニケーションを重視する子に向いてるし、オンライン型は時間や場所の自由がきくのが魅力。ただ、小学生が一人で学習を進めるにはちょっとしたサポートが必要かもしれないから、親御さんがどれくらい関わるべきかも事前に確認しておくと安心だよ。
お金のことも大切だよね。月謝だけじゃなくて教材費とか追加の費用がかかることもあるから、トータルで考えるのがポイント。でも、費用だけで決めるんじゃなくて「この教室でどんな成長が期待できるか」をしっかり見極めるのが大事だよ。子どもの未来への投資だもんね!
意外と見落としがちなのが、学びを続けるためのフォロー体制。定期的に成果を確認したり、保護者に報告があったり、子どもの進捗をきちんと見てくれる教室だと安心感が違うよね。こういう細やかなサポートがあると、子どももやる気が続きやすいんだ。
研究では、週1回の教室通いと自宅での復習を組み合わせるスタイルが小学生に一番効果的って言われてるよ。あと、3ヶ月くらいの短い目標を設定して、それをクリアするたびに次のステップに進むのが、子どものモチベーションを保つコツみたい。
こうしていろんなポイントを押さえて教室を選ぶのって大事だけど、やっぱり最後に決め手になるのは、子ども自身が「ここ楽しい!もっとやりたい!」って思えるかどうかだよね。プログラミング教室で育まれる思考力や創造力は、子どもが主体的に学ぶ中でこそ伸びていくものだから。
さあ、一緒に子どもの未来を広げる素敵な教室を見つけていこう!
[参考文献]川崎教育研究所「小・中学校におけるプログラミング教育の研究」
6.プログラミング学習を成功させるための家庭でのサポート
小学生がプログラミングを学ぶなら、家庭でのサポートがめちゃくちゃ大事!文部科学省の調査でも、親がちゃんと関わることで、子どものやる気や理解がぐっと伸びるって分かってるんだよね。
まず一番大切なのは、子どもの興味に寄り添うこと。「なんでこうなるんだろう?」とか「これどうなってるの?」って好奇心を持ったときに、「一緒に考えてみよう!」って付き合ってあげるのが大事。たとえば、家にある自動ドアとかタイマー機能の仕組みを話題にすると、自然とプログラミング的な思考に興味を持つようになるよ。
次に、家庭での学習時間をどうするかって話。小学生の集中力を考えると、1回30分くらいがちょうどいいんだって。そのくらいの時間を週に何回か取ってあげて、学校での学びをフォローすると、学習習慣が自然に身についていくよ。
それから、子どもの「やる気スイッチ」を押すためには、成功体験をいっぱい褒めてあげることがポイント。「お!こんな工夫したんだね!」とか「そこに気づくなんてすごい!」みたいな声かけが、自信につながるんだよね。結果よりも「考えた過程」をしっかり認めてあげると、もっと伸びるから意識してみて。
それとね、家庭での日常生活を学びと結びつけるのも効果的だよ!たとえば、料理の手順を一緒に考えたり、お出かけのスケジュールを立てたりするのも、プログラミング的な考え方の実践になるの。「これを先にやって、次にこれをやろう」って、論理的に順番を考える練習になるんだ。
でも、注意したいこともいくつかあるよ。親が先回りして「あ、こうすればいいよ!」って答えを教えすぎちゃうと、子どもの「考える力」を奪っちゃうことも。ちょっと遠くから見守るくらいがベスト。失敗も学びのうちだから、じっくり待ってあげよう。
あと、プログラミングに夢中になるのはいいけど、他の教科がおろそかにならないように気をつけてね。学校の先生と相談しながら、バランスよく学べる計画を立てるのがおすすめ!
デジタル機器の使いすぎにも注意だよね。目の健康とか生活リズムを守るために、使用時間を決めておくといいよ。そのときに「なんでこのルールが必要なのか」を子どもと話し合って決めると、納得して守りやすくなるよね。
そして、何よりも大事なのが、親子のコミュニケーション!子どもが「今日こんなこと学んだんだよ!」って話してくれたら、「すごいね!どんな風にやったの?」って興味を持って聞いてみて。一緒に課題に取り組んだりすると、学ぶ楽しさを共有できていいよね。
家庭学習の効果をもっと高めるためには、「達成感の共有」と「振り返りの習慣」が大事なんだって。週末に「今週こんなことできたね!」って家族で話し合ったり、「次はどんなことやってみる?」って一緒に計画を立てたりするのもおすすめだよ。
困ったときは、すぐに答えを教えるんじゃなくて、「どうしてそう思ったの?」とか「他にいい方法があるかな?」って質問してみて。そうすると、自分で考える力がぐんぐん育つんだよね。
こんな風に、家庭でのサポートって、子どもの学ぶ意欲を育てる大きなカギになるんだよ。焦らず、楽しく一緒に取り組んでいくことで、プログラミングの学びもどんどん深まっていくから、一歩ずつ進んでいこうね!
[参考文献]文部科学省「小学校段階におけるプログラミング教育の在り方について」
7.実際にプログラミング教育を始めた保護者の声
小学生のプログラミング教育って、本当にすごい変化をもたらしてるんだよ!学習意欲とか思考力の面で「おおっ」って驚くような効果がたくさん報告されてるの。特に注目したいのは、小学生が論理的に考えられるようになったり、問題を解決する力がぐんぐん伸びてるってこと。文部科学省の調査でも、プログラミングを通じて「自分で考える」「あれこれ試してみる」っていう主体的な学びの姿勢が育ってるって結果が出てるんだよね。こういう力って、他の教科でも大きな助けになるよね!
実際、小学生がプログラミングを学ぶと、教科を超えた学びの深まりが見られるんだって。例えば、算数では「こうすればうまくいくんだ!」って論理的に考える力が伸びたり、理科では現象をより深く理解できるようになったり。国語では文章の構成をきちんと整理する力もアップしてるみたいで、めちゃくちゃ幅広い効果があるんだよね。そして、特にすごいのは、小学生が自主的に学ぼうとする姿勢が育つこと。プログラミングで身についた「試行錯誤してみよう!」っていう気持ちが、他の場面でも役立ってるんだって。課題解決の見通しを立てたり、計画を立てて進めたりする力もぐっと伸びてるみたい。
家庭生活でも、このプログラミングの学びがすごく生きてるんだよね。計画的に動いたり、段取りを考えるのが自然にできるようになってくるし、家族と「今日こんなことを学んだんだよ!」って話すことで、コミュニケーションもどんどん活発になるんだって。論理的に考える力がつくと、生活習慣の改善にもつながるから、すごくいい影響を与えてくれるんだね。
それにね、長期的な視点で見ると、プログラミング教育って情報社会に対応する力を育てるって意味でも超重要!今みたいにテクノロジーがどんどん進化してる時代に、小学生のうちから「プログラミング的な考え方」を身につけることで、将来の選択肢がどんどん広がるんだよ。情報技術をどう使いこなすかの基本を学ぶだけじゃなくて、情報モラルとか正しい使い方の基礎も身につくから、本当に価値があると思うの。
もちろん、最初にプログラミングを始めるときは「難しくないかな?」とか「画面ばっかり見てて大丈夫?」って心配もあるよね。でも、ビジュアルプログラミングみたいな発達段階に合った教材を使えば、そんな不安も解消できるんだ。あと、適度に休憩を取ったり、学習時間をしっかり管理すれば、健康面もバッチリ守れるから安心だよ!
プログラミングを続けて学ぶには、やっぱり周りのサポートが大事。小学生が一生懸命取り組んだら「頑張ったね!」ってしっかり褒めてあげたり、学校で習ったことと結びつけて「これって理科の実験にも使えるよね!」みたいな声かけをするのが効果的なんだって。日常生活でプログラミングと関係のある場面を見つけて一緒に楽しむのもいいよね。
実は、1年以上続けてプログラミングを学んだ小学生には、特に問題解決能力がぐんと伸びる傾向があるんだって。これって、単なるスキルの習得じゃなくて、人間としての成長にもつながってるってことだよね!創造力や新しいアイデアを生み出す力もぐっと伸びてくるみたいで、未来のリーダーを育てる教育って感じがするよね。
家庭での学習でも「今日はこれやってみよう!」って計画を立てたり、新しいことにチャレンジする姿勢がどんどん定着してるみたい。こういう姿勢って、将来のどんな学びにも役立つし、一生ものの力になるよね。特に、自己調整能力が高まるっていうのは、生涯学習の基礎としてもすごく意味があることだと思うの。
プログラミング教育って、子どもたちの可能性を広げて、これからの未来を切り拓いていく力を育てる素敵な学びだなって改めて思うよ!
[参考文献]川崎教育研究所「小・中学校におけるプログラミング教育の研究」
https://kawasaki-edu.jp/index.cfm/7,146,c,html/146/32-093-112.pdf
8.まとめと次のステップ
プログラミング教育ってさ、なんだかちょっと難しそうなイメージあるよね。でも実は、小学生の「考える力」を育てるうえで、めっちゃ効果的なんだよ!今回は、プログラミング教室での学びや、小学生にどんな変化をもたらすのかについて、わかりやすくお話ししていくね。
まず大事なのは、プログラミング教育が「ただの技術のお勉強」じゃないってこと!小学生がプログラミングを学ぶと、「どうやったらうまくいくのかな?」とか「この順番だともっとスムーズにできるかも!」って、物事を順序立てて考えたり、問題を解決したりする力が身についてくるの。しかも、試行錯誤しながら自分なりの答えを見つけていくから、「チャレンジするのって楽しい!」って思えるようになるんだよね。
それにね、算数とか理科とか、いろんな教科の学びにもすごく役立つんだ。たとえば算数だと、図形の性質をプログラミングで描きながら学ぶと、ただ計算するよりずっと理解が深まるし、理科ではセンサーを使った実験で、観察力や分析力がぐーんとアップするんだって。国語でも、物語を論理的に組み立てる力がついたりして、プログラミングがいろんな教科と相性バッチリなのがわかるよね。
でも、プログラミング教育をもっと広めるには、いろんな課題もあるんだよね~。たとえば学校の先生たちがもっと教え方に慣れるための研修とか、パソコンとかタブレットの準備を整えるとか、学校全体でのサポート体制をしっかり作らなきゃいけないんだ。それから、家でも子どもが「これ楽しい!」って思いながら学べる環境を作るのもすごく大事。ママやパパが一緒に考えたり、応援してくれると、子どもはやる気が倍増しちゃうんだよね!
次に目指すべきは、小学生一人ひとりのペースに合わせた柔軟なカリキュラムを作ること!興味のあることや得意なことをどんどん伸ばせる教材とか、楽しみながら学べる方法をもっと増やしていきたいよね。それに、どれくらい「考える力」が育ってるかをきちんと見ていく方法も整えたいところだね。
あとね、地域のみんなとの協力もめっちゃ大切!地元の企業とか団体が一緒にプログラミングの体験を提供してくれたら、実際に「こんな風に役立つんだ!」ってリアルに感じられるじゃん?そういう実践的な学びがあると、もっとワクワクしちゃうと思うんだ。
これからのプログラミング教育って、ただコンピュータの使い方を覚えるだけじゃなくて、小学生が「自分にはこんな可能性があるんだ!」って気づけるきっかけをいっぱい作れるものだと思うの。学校や家庭、地域がみんなで協力して、どんどん面白くて役立つ学びの方法を探していけたら最高だよね。変化が激しい世の中だからこそ、小学生が自分の力で未来を切り開けるように、みんなでサポートしていこうよ!
[参考文献]文部科学省「小学校プログラミング教育の手引(第三版)」
https://www.mext.go.jp/content/20200218-mxt_jogai02-100003171_002.pdf
川崎教育研究所「小・中学校におけるプログラミング教育の研究」
https://kawasaki-edu.jp/index.cfm/7,146,c,html/146/32-093-112.pdf
マイクラで楽しくプログラミングを学べる!エドモンドプログラミングスクール

エドモンドプログラミングスクールでは、教育版マインクラフト(Minecraft)を使用した子どもたちが夢中になれる ゲーム感覚のカリキュラムで、プログラミングの基礎から実践力までしっかりと学ぶことができます。
「プログラミングって難しそう…」「他の習い事も忙しいけどできるかな…」と感じる初心者でも大丈夫! お子さまが「もっとやりたい!」と感じられる仕組みで、小学1年生からでも楽しく学習を続けられます。さらに好きな開校日を選んで通えるから、習い事の両立もできます!
まずは、エドモンドプログラミングスクールの無料体験教室に参加してみませんか? 普段は見られない子供の集中した姿が見られる楽しい体験会です!
お近くの教室はこちらから
https://www.edmondo.jp/search/