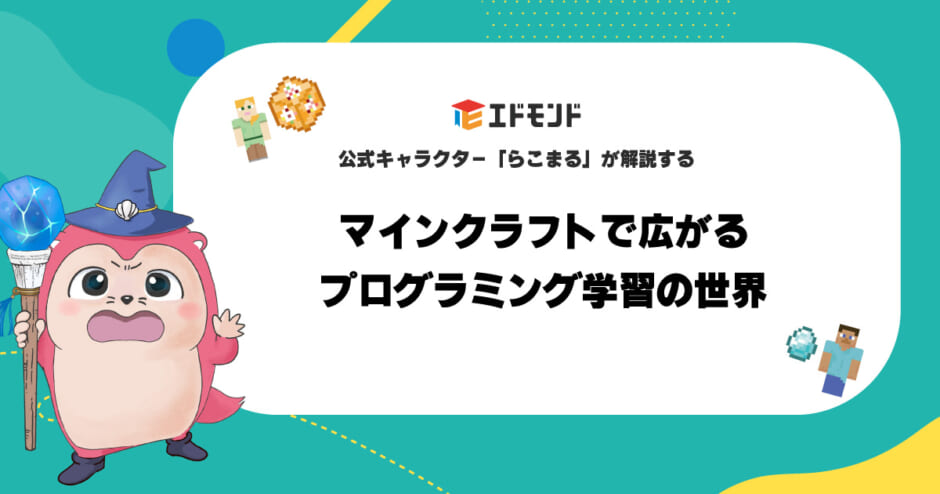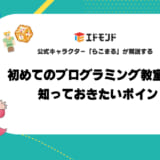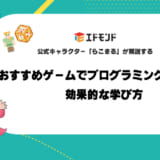- はじめに
- マインクラフトとは?
- マインクラフトを使ったプログラミング教育のメリット
- 子ども向けプログラミング教室の選び方
- マインクラフトを活用した革新的な学びの仕組み
- 保護者としてのサポート方法
- まとめ
1.はじめに
プログラミング教室で最近すごく注目されてるのが、マイクラ(マインクラフト)を使った授業なんだよ。教育研究者のAlawajee & Delafield-Butt(2021)が面白い発見をしていて、マイクラを使うと子どもたちのやる気がぐんと上がって、言葉の発達も進むし、普段の勉強にもいい効果があるみたいなんだ。
マイクラがここまで広がってきた理由って、とってもユニークな特徴があるからなんだよね。「サンドボックスゲーム」って呼ばれてて、「これをやらなきゃいけない」みたいな決まりがないの。だから子どもたちは自分のペースで進められて、プログラミングの基礎が自然に身についていくんだ。それに、この自由な環境のおかげで、子どもたちの創造性もどんどん広がっていくみたいだよ。
最近はね、GIGAスクール構想の影響で、オンラインでの活動がすごく増えてきてるんだ。プログラミング教室でも、マイクラみたいなメタバース空間を使うところが増えてきて、たくさんの自治体が新しい取り組みを始めてるよ。教育の現場がデジタル化していく中で、マイクラは先進的な例として注目されてるんだ。
マイクラを使ったプログラミング学習では、予想もしなかったような効果も出てきてるんだよ。コミュニケーション力や、友達と協力する力、リーダーシップみたいな社会性が育つんだって。Rospigliosi(2022)の研究でも、マイクラみたいなオンラインゲームが教育に与える影響について、これからもっといろんな発見があるんじゃないかって期待されてるんだ。特に、子どもたちの問題解決能力や論理的な考え方がよくなるって言われてるよ。
それにね、マイクラって世界でもすっごく注目されてるんだ。TechJuryのレポートによると、2023年1月の時点で、なんと1億7350万人以上の人が使ってるんだって。もうプログラミング教室だけじゃなくて、普通の学校の授業でも使われ始めてるくらいなんだよ。
マイクラの一番いいところって、やっぱり自由度が高いことかな。子どもたちは仮想空間で自分のキャラクターを動かして、ブロックを積み上げて建物を作ったり、アイテムを工夫したり、いろんなことができるんだ。そうやって遊んでるうちに、プログラミング的な考え方が自然に身についていくっていうわけ。
これから、こういった研究結果を見ながら、マイクラを使ったプログラミング教育の特徴や効果について、もっと詳しく見ていこうと思うんだ。特に小学生の子どもがいる保護者の人に向けて、プログラミング教育の選択肢としてマイクラの可能性を、できるだけ分かりやすく説明していきたいな。デジタル時代を生きる子どもたちにとって、こういった学びがどんな意味を持つのか、一緒に考えていければいいなって思うんだ。
[参考文献]信大マイクラの取り組みの報告「マインクラフトを活用した教育研究のレビュー」
https://soar-ir.repo.nii.ac.jp/record/2001978/files/cril22-2.pdf
2. マインクラフトとは?
マイクラ(マインクラフト)って、今の子どもたちの間で爆発的に人気なゲームなんだよ。何が特徴かって言うと、立方体のブロックを使って好きな建物や町を自由に作れるところなんだ。最近は教育の現場、特にプログラミング教室でもすごく注目されてて、子どもたちが作った作品がたくさんネットに上がってるの見たことあるかな?
プログラミング教室で使ってるのは、普通のゲーム機で遊ぶマイクラとはちょっと違う「Minecraft: Education Edition」っていう教育用のバージョンなんだよ。これにはプログラミング言語と組み合わせられる機能が入ってて、より学習に使いやすくなってるんだ。研究してる人たちが見てたら面白いことが分かってきて、これを使った学習で子どもたちは新しいアイデアを考えたり工夫したりすることに夢中になって、創造的な活動がすごく活発になるみたいなんだ。
教育版マイクラの面白いところってね、「エージェント」っていうロボットがいることなんだよ。子どもたちはこのエージェントを使ってプログラミングの基本を学んでいくんだけど、操作方法が「Scratch」に似てるから、子どもたちがすぐに使えちゃうんだって。すごいよね!
マイクラを使ったプログラミング教室では、創造性が伸びるのはもちろん、友達と一緒に活動する力も育つみたいなんだ。仮想空間で友達と相談しながら何かを作っていくって、子どもたちにとってすごく大切な経験になるんだって。実際にアンケートを取ってみたら、「みんなで町を作るのが楽しかった」「人と相談しながら作業することの大切さが分かった」っていう声がたくさんあったみたいだよ。
プログラミング教室では、マイクラの特徴を使っていろんな学習ができるんだ。例えば、道路作りを自動化したり、チームで町の設計を考えたり。そうやって自然とプログラミング的な考え方や協力する力が身についていくの。面白いのは、「間違った命令を出すとエージェントも間違って動く」っていう経験から、論理的に考えることの大切さを学べるところなんだよ。
子どもたちはマイクラの中で自分のキャラクターを動かして活動するんだけど、この体験を通じて「順番に処理する」「繰り返す」「条件で分ける」っていうプログラミングの基本が理解しやすくなるんだって。画面で結果がすぐ見られるから、自分のプログラムが合ってるかどうかもすぐ分かるし、とても分かりやすいみたいだよ。
活動の様子は動画にまとめてYouTubeとかで公開することもあるんだ。自分たちの作品を色んな人に見てもらえるって、子どもたちのやる気をすごく高めてくれるみたい。それに、たくさんの人に見てもらうにはどうしたらいいかって考えることで、情報発信の難しさや工夫の仕方も学べるんだって。
研究してる人たちが見つけた面白いことなんだけど、マイクラのプログラミング教室に参加した子どもたちは、「世の中のことって、順番通りにやる・繰り返す・条件で変えるみたいな動きに分けて考えると、すごく分かりやすい」って気づくみたいなんだ。これってプログラミング的な考え方の基本になる、大切な発見だと思わない?
[参考文献]JAET論文 マイクラ 中川「マインクラフトの教育版(Education Edition)とその活用方法についての解説」
https://www.jaet.jp/repository/ronbun/JAET2018_A-2-6.pdf
3. マインクラフトを使ったプログラミング教育のメリット
教育研究でマイクラを使ったプログラミング教育を見てみたら、すごく面白い効果が4つも見つかったんだよ。まず子どもたちのやる気がぐんと上がるんだって。それから言葉の力も伸びるし、普段の勉強にもいい影響があるみたい。あと、友達と協力する力とかリーダーシップみたいな社会性も育つんだって、すごいよね。
面白いのがね、マイクラって子どもたちにとってネット上の「居場所」になってるみたいなんだ。研究者の人たちが調べたら、この居場所には4つの特徴があるって分かってきたんだよ。まずは放課後の公園みたいな「遊び場」になってるところ。それから人との付き合い方やネットの使い方を学ぶ「学び場」としての役割。それに、学校とか普段の生活に居場所がない子の「避難所」みたいな役割もあるんだって。最後は、自分に合った居場所を探して「さまよう場所」としての役割もあるみたい。
プログラミング教室では、特に「遊び場」と「学び場」の部分を大切にしてるんだよ。子どもたちは自分のキャラクターを動かして、ブロックで建物を作ったり、アイテムを工夫したり、いろんなことができるんだ。そうやって遊んでるうちに、自然とプログラミング的な考え方が身についていくの、面白いよね。
ネット上での活動って、普段とは違うコミュニケーションができるのも特徴なんだ。例えば、自分の良いところだけ見せたり、あんまり見せたくないところは隠せたりするでしょ?相手のことをよく知らないからこそ、逆にいいイメージを思い描いちゃったり。メッセージをじっくり考えて送れたりするのも、オンラインならではだよね。
マイクラでのやりとりって、普通のネットでのコミュニケーションとはまた違う特徴があるんだよ。見た目とか、どんな立場の人かとか、そういうのは隠しつつ、自分が見せたいところだけ見せられる。で、見てる側は、分からないところを勝手にいいように想像しちゃう傾向があるみたいなんだ。
プログラミング教室では、子どもたち同士でよく話し合う機会があるんだよ。今日は何をするかを相談したり、作業中にも意見を出し合ったり。そうやってネット上で他の子と積極的に話したり、協力したりする経験ができるんだ。
それとね、面白いことに、マイクラの操作って、子どもの方が大人より上手いことが多いんだよ。だから、あえて子どもが大人に教える機会を作ることで、子どもたちの自信になったり、自分から行動する力が育ったりするみたいなんだ。
これって単なるゲーム遊びじゃなくて、ちゃんとした教育プログラムとして作られてるんだよ。子どもの居場所作りだけじゃなくて、考える力やコミュニケーション力を育てるっていう目標もあるの。ネット上で子ども同士が話し合えるような工夫もされてるし、対話を重視した活動になってて、すごく考えられてるんだ。
[参考文献]信大マイクラの取り組みの報告「マインクラフトを活用した教育研究のレビュー」
https://soar-ir.repo.nii.ac.jp/record/2001978/files/cril22-2.pdf
4. 子ども向けプログラミング教室の選び方
プログラミング教室を選ぶときのポイントって、実は3つあるんだよ。「カリキュラム内容」「指導方法」「教室の環境」なんだ。研究してる人たちが調べてみたら、この3つが子どもの学びにすっごく影響するって分かったんだって。
カリキュラムを見るときは、子どもの目標とか将来を広げられるような中身になってるかどうかを確認するといいんだ。特にマイクラを使う教室だと、ただ遊ぶだけじゃなくて、創造力とか論理的な考え方が育つような、しっかりした仕組みがあるかどうかをチェックしてみてね。
指導の仕方で大切なのはね、子どもが「やりたい!」って思えるような感じで、一人一人の伸び方に合わせてくれるかってところなんだ。研究してる人たちによると、子どもが自分からやりたくなる環境だと、やる気も出るし、長く続く成長につながるみたいだよ。それと、一人で学ぶ時間とみんなで学ぶ時間のバランスも見てあげるといいかも。
学習環境で特に気をつけたいのは、子どもが「分からない」ってなったときにすぐ聞ける雰囲気があるかどうかなんだよ。質問にすぐ答えてくれて、子どもの分かり具合に合わせて説明してくれる環境じゃないと、長く続かないんだって。あと、子どもの理解度を見ながら柔軟に進めてくれるかも、大切なポイントだね。
教室選びのときは、無料カウンセリングとか体験レッスンを使うといいよ。カウンセリングなら、教室のやり方とか環境について細かく聞けるし、子どもに合ったアドバイスがもらえるんだ。体験レッスンだと、実際の雰囲気や教え方を体験できて、子どもと合うかどうか分かりやすいんだって。
お金のことも気になるよね。調べてみたら、プログラミング教室って、中身や環境によって値段がけっこう違うみたいなんだ。入会金とか教材費の最初の出費、月謝とか受講料の払い方が融通きくかとか、前もって確認しておくといいよ。後から「えっ、こんなにかかるの?」ってびっくりしないためにも、お金の仕組みはちゃんと見ておこうね。
子どもの成長を長い目で見るのも大切なんだよ。良さそうな教室は、プログラミングの基礎から始めて、少しずつ難しくしながら論理的な考え方を育てていく計画を持ってるんだ。こういう長期的な計画があるかどうかも、教室を選ぶときの大切なポイントになるよ。
それと、対面かオンラインかも大事な選択なんだ。対面なら直接やり取りできて、子どもの分かり具合がすぐ分かっていいんだけど、オンラインは時間や場所の制限が少なくて、子どものペースで進められるんだって。家庭の状況とか子どもの学び方に合わせて選んでみてね。
教室を選ぶときは、これまでの実績とか親の評判とか、いろんな角度から見てみるといいよ。特に大切なのは、子どもが楽しく続けられそうな雰囲気があることと、将来の可能性を広げてくれる質の高い教育をちゃんとやってるかってことなんだ。
[参考文献]『卒業生に聞いたプログラミングスクールの選び方!7つの基準を解説』
https://www.sejuku.net/blog/147794
『失敗しないプログラミングスクールの選び方を徹底解説!どんな基準で選ぶべき?』
https://www.agaroot.jp/datascience/column/programming-school-choice/
5. マインクラフトを活用した革新的な学びの仕組み
マインクラフトって、子どもたちが勝手に学んじゃう不思議な仕組みがあるみたいです。学習指導要領が言う「生きる力」にピッタリだって、先生たちの間で話題になってるくらい。
面白いのが、誰も教えてくれないってこと。子どもたちは自分で考えて、調べて、失敗して、また挑戦する。そうやって自然と問題解決力が育つみたい。友達と相談しながら進めるから、人とのコミュニケーションも上手くなっていくって。
それと、やりたいことが自由にできるのもすごいところ。思いついたアイデアを好きなように形にできるんです。最初は真似っこから始まるけど、そのうち自分なりの工夫を加えていって。そうやって創造力とか論理的な考え方が育っていくみたい。
電子工学の基礎とか論理回路の仕組みも、気づいたら分かるようになってる。レッドストーン回路とかコマンドブロックで遊んでるうちに、プログラミング的な考え方が身についちゃう感じ。
普段の勉強とも結びついてて、理科なら実験の手順を考える力が、社会なら歴史的な建物の理解が、算数なら空間を把握する力が育つみたい。教室だけじゃ分からないような深い理解につながるって。
パソコンの基本的な使い方も自然と上手くなっていく。キーボードやマウスの操作、コマンドの打ち方なんかも、遊びながら覚えられちゃう。
子どもたち自身が学びの主役になれるのが、一番いいかも。誰かに教えてもらうんじゃなくて、自分で課題を見つけて、解決方法を考えて、やってみる。その達成感が次の挑戦につながっていくって。
これまでの教え方じゃ難しかった「生きる力」が、マイクラだと自然と育つみたい。子どもたちは遊びながら、これからの時代に必要な力を身につけていけるって、すごくない?
一人一人のペースでゆっくり進められるのもいいところ。分からないところは立ち止まって考えたり、友達と相談したり。自分なりの速さで理解を深められる感じ。
オンラインだから、失敗しても何度でもやり直せる。それが新しいアイデアを生むきっかけになってるみたい。失敗を恐れずにチャレンジできるのって、子どもたちにとって大切だよね。
建物作ってるうちに素材や構造に興味持って、本物の建築や工学のこと調べ始めたり。そういう風に興味がどんどん広がっていって、知識も深まっていくみたい。
将来のことを考えると、ここで育つ力って大事な土台になりそう。自分で考えて、計画して、実行する。その結果を振り返って、また次に挑戦する。そういうサイクルを繰り返してるうちに、「学び方を学ぶ」力が自然と身についていくって。
マイクラを使った学びって、今までの教育じゃ見落としがちだった創造性とか主体性、探究心を引き出せるみたい。これからの時代を生きる子どもたちにとって、すごく大切な経験になりそうだよね。
[参考文献]1. 日本財団ジャーナル「主体性、創造力、探究心――マインクラフトが教育に適した理由」
https://www.nippon-foundation.or.jp/journal/2023/96718/education
2. 東洋経済education×ICT「日本初マイクラのプロが語る驚きの教育効果」
https://toyokeizai.net/articles/-/441222
3. まなぶてらすブログ「なぜマインクラフトが教育に!?その秘密は生きる力とアクティブラーニング!」
6. 保護者としてのサポート方法
プログラミング教室での学び、特に大切なのは親の適切なサポートだよ。子どもの学ぶペースを大切にして、マイクラみたいな学習ツールを上手く使いながら、長い目で支援していくことがポイントらしい。
基本は、子どもが主体的に取り組めるようにすること。プログラミング教室で大事なのは、子ども自身が興味を持って、失敗しながら理解を深めていくプロセスなんだって。親は見守りながら、マイクラでの活動を含めて、タイミングを見て声をかけたり支援したりするといいみたい。
「それってどうなってるの?」「どうしてそう考えたの?」って聞くと効果的みたい。プログラミング教室での活動を家でも振り返って、子どもが自分の考えを言葉にして、もっと深く理解できるように。マイクラで作ったものや発見したことを説明させると、考えを整理したり表現力を高めたりできるって。
つまずいたときは、すぐに答えを教えちゃダメみたい。「どこで困ってるの?」「他にどんなやり方があるかな?」って問いかけると、子どもが自分で解決する力が育つらしい。
家での学習環境作りも大切。マイクラの時間を確保したり、プログラミング教室の教材をチェックしたり。でも、時間や方法は子どもの自主性を尊重して、押しつけないようにした方がいいって。
長い目で見守るのも大切。プログラミング教室での学びは、すぐには成果が出ないものだから。子どもの成長に合わせて、少しずつ支援していく感じ。時には立ち止まったり遠回りしたりするけど、それも学びの一部として考えるといいみたい。
達成感や自信を育むサポートも忘れちゃダメ。マイクラでちょっとした進歩や工夫を見つけたら、具体的に褒めてあげると、学習意欲が高まるって。「どんな工夫したの?」「それ面白い考えだね」って声かけると、創造性や挑戦する気持ちが育つみたい。
デジタル社会だから、親も情報集めて、子どもと一緒に学ぶ姿勢が大切だって。プログラミング教室やマイクラの情報を知っておくと、子どもの学習をもっと効果的に支援できるらしい。一緒に課題に触れることで、共通の話題も増えるし、コミュニケーションも深まるって。
子どもの準備状態も大切。マイクラやプログラミング教室への興味や、基本的な操作力とか、子どもの状況をよく見て、無理なく進められるように支援するといい。特に始める時期は、子どもの心の準備ができてるか見極めることが大切だって。
結局、親のサポートって、子どもが主体的に学べるように支える大切な役割があるみたい。子どもが自分で考えて、失敗しながら成長していけるよう、適度な距離感で支援を続けることで、プログラミング教室での学習効果も最大限に引き出せるって。
[参考文献]『大学の一般教育としてのプログラミング教育』
https://www.jstage.jst.go.jp/article/isciesci/62/7/62_266/_pdf/-char/ja
7. まとめ
マイクラを使ったプログラミング教育って、今までの教え方とはぜんぜん違う可能性を持ってるよ。研究を見ると、子どもたちがやる気いっぱいになって、自然に友達とコミュニケーション取れるようになったり、協力する力が育ったりするみたい。
オンライン空間だからできる学びが面白いよね。子どもたちは仮想空間の中で自由に考えて、失敗して、また挑戦できる。友達同士で意見交換したり、一緒に問題を解決したりする姿もよく見られるって。
プログラミング教室での学びは、プログラミングの技術だけじゃないみたい。マイクラを通じて、論理的な考え方や創造力、問題を解決する力とか、これからの時代に必要な力が自然と育つって。
それに、子どもたちの個性や学び方に合わせて柔軟に対応できるのも良いところ。一人一人が自分のペースで課題に取り組めて、理解を深められる。マイクラの自由度の高さのおかげで、子どもたちは自分のアイデアを形にしやすいみたい。
オンラインでのコミュニケーションには、対面とは違う良さがあるって。自分の見せたい部分を選んで表現できて、相手との関係も少しずつ築いていける。情報が不完全だからこそ、かえって積極的なコミュニケーションが生まれやすいみたい。
プログラミング教室は、勉強する場所以上の意味を持ってきてる。「遊び場」として自由に交流したり、「学び場」としていろんな体験ができたり。子どもたちは安心して自己表現や挑戦ができて、それが自信につながってるみたい。
教科の勉強との結びつきも面白いよね。科学や歴史の勉強でも、マイクラでの体験が理解を深めるのに役立つって研究でも分かってきた。メタバースでの学びは、教科の枠を超えた新しい学び方を可能にするみたい。
課題もあるけどね。子どもたちが続けて参加したくなる工夫とか、効果的な教育支援の方法とか、学習効果をちゃんと確認する方法とか。こういうことに取り組みながら、もっと良い学習環境を作っていく必要がありそう。
メタバースでの教育支援には、まだまだ可能性がありそう。難しい概念を体験して理解したり、一人一人の興味や理解度に合わせて学んだり。今までの教え方じゃ難しかったことが、できるようになるかも。教育支援の方法も日々進化してて、新しい技術の開発と実践が期待されてる。
このように見ると、マイクラを使ったプログラミング教室は、デジタル時代の新しい学び方として、すごい可能性を秘めてるよね。子どもたちが主体的に学び、創造性や協力する力を育む場として、これからもっと重要になっていくと思う。
将来的には、メタバース空間での学びがもっと発展していくんじゃないかな。その中で、マイクラを使ったプログラミング教室は、新しい時代の教育モデルとして重要な役割を果たしていくと思う。子どもたちが生き生きと学び、成長していける環境作りに向けて、まだまだ可能性を探っていく必要がありそうだよ。
[参考文献]信大マイクラの取り組みの報告「仮想空間上での小学生と大学生の交流活動」
https://soar-ir.repo.nii.ac.jp/record/2001978/files/cril22-2.pdf
マイクラで楽しくプログラミングを学べる!エドモンドプログラミングスクール

エドモンドプログラミングスクールでは、教育版マインクラフト(Minecraft)を使用した子どもたちが夢中になれる ゲーム感覚のカリキュラムで、プログラミングの基礎から実践力までしっかりと学ぶことができます。
「プログラミングって難しそう…」「他の習い事も忙しいけどできるかな…」と感じる初心者でも大丈夫! お子さまが「もっとやりたい!」と感じられる仕組みで、小学1年生からでも楽しく学習を続けられます。さらに好きな開校日を選んで通えるから、習い事の両立もできます!
まずは、エドモンドプログラミングスクールの無料体験教室に参加してみませんか? 普段は見られない子供の集中した姿が見られる楽しい体験会です!
お近くの教室はこちらから
https://www.edmondo.jp/search/